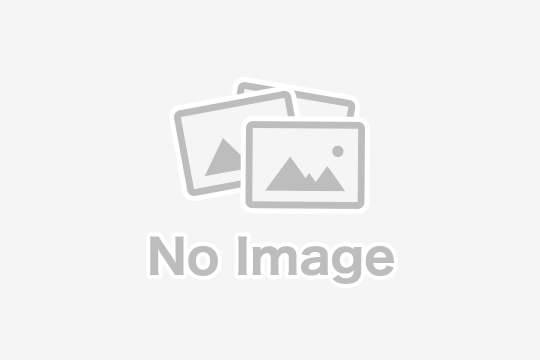本日は色彩検定について書いていこうと思います。
シリーズものにして、受けようかな?今勉強している人向けに役に立つように書いていきたいと思います。 出来るだけくどくならず、簡単に! 色彩検定について https://www.aft.or.jp/ サイトを見て頂けるとわかるような資格です。 そもそもこの手の資格は自己満か、指標に使うかのどちらかです。 車の免許はそれがないと運転出来ないですよね? 色彩検定の資格って無くても別に何でもできます。 つまり、持っているという自己満足か、面接や何かやる時に看板に使うわけです。 僕は知識が欲しかったので、受けました! また別の理由(笑)、まあ自己満の分類ですね。 色の知識ついでに資格をどうせなら取ろうというのが目的で取りました。
まず色彩について
色彩は面白いし、腹が立つし、興味深い。 一度は皆さん思ったことがあるかもしれません。 「自分が見ている赤と他人が見ている赤は同じ色なのだろうか?」 僕はこれを解決するために色彩検定を受けたといっても過言ではありません。 まず大前提として、人間は生物で動物、哺乳類に分類されています。 ←これめちゃ大事 動物と認めたくない人がいるかもしれませんが、飲み込んでください。 では、人間以外の動物の目はどのように見えているのか? ・目が見えない動物:退化した生物等 ・1つの色しかわからない動物:アリ、カマキリ、イタチ、リス等 ・2つの色がわかる動物:犬、猫、シカ等 ・3つの色がわかる動物:人間、チンパンジー、猿等 ・4つの色がわかる動物:スズメ、タカ、カラス等 では、色彩検定はどこで行われる試験なのか? 「3つの色がわかる動物」特に人間がどのように見えているか、感じているかを問う資格になります。 つまり「色彩検定」色彩の資格ではなく、正確には「色彩による人間の目の構造と心理影響、効果に対する資格」ということです。 意味がわかりませんね(笑) 例えば、「赤」=「興奮する色」「目立つ色」とされます。 それは人間がそのように感じるだけで、人間が勝手に人間の為に分類した結果、それが正解ということです。 = 多数決の正解 物理的なことでいえば、同じ明るさ、同じ彩度「赤」「青」「緑」を用意した場合、同じ効果でなければなりません。 それを心理的尺度でこうあるべきと位置づけをするというものです。 僕はこれがなるほど!と思いつつ、少し平等性にかけてイラッとしました(笑) この資格はこういうものだという若干腑に落ちない感じで受け入れないと進みません。 「僕は緑に興奮するんだ!」 確かにそういった人もいるかと思いますが、世の中の一般的なことはこうなんだよ。 と教えてもらえる資格と思っておきましょう。 本日はここまでにしておきます。 次回は色彩検定の種類と内訳、合格率等をお話していきたいと思います。