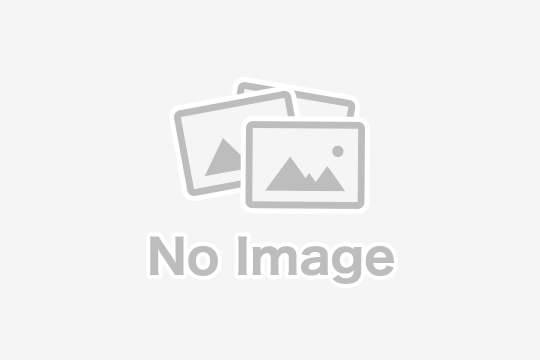独学で色彩検定1級をいきなり取りに行くための勉強内容
シリーズものにして、受けようかな?今勉強している人向けに役に立つように書いていきたいと思います。 出来るだけくどくならず、簡単に! 色彩検定について https://www.aft.or.jp/ 前回の続きを話していきましょう。 色彩検定1級の一次試験に関しては省かせて頂きます。 はっきりと公式テキストから出るので、それを丸ごと覚えて下さい。 あとは過去問過去3年分を満点になるまでやって下さい。 どれくらいの勉強量、勉強時間を聞く人がいますが、無意味です。 あなたが覚えられるだけの勉強量で勉強時間です。 1週間の人もいれば、5年の人もいるかもしれません。 そんなことを聞くよりも合格率を見る方が目安になります。 2024年の色彩検定1級合格率:41%と出ています。 つまり1次試験はかなりの人数が通っているということです。 そして2次試験で落ちて合計41%です。 仮に1次試験で50%の合格率で二次試験も50%の合格率だとした場合、半分の半分です。 つまり25%ということになります。 1次試験が他の2級、3級と同じ70%だとした場合、2次試験の合格率は約60%ということになります。 何が言いたいかというと、一次試験はテキスト読みなさい。以上です。(笑)
色彩検定二次試験対策について
色彩検定1級の二次試験について調べると何やら不安を煽る内容が多々出てきます。 「明確な対策はありません」「○○○○年対応」「新○○」とかとか え?常に新しくなっているの?明確な対策がない?可能性のある対策はしておかなきゃ!スクールが確実じゃない!? こんな心境に陥るわけですよ。。 ふざけんなー! ちなみに僕も思いました。。(笑) 何を対策したらよいかわからないので、自己判断で良さそうなのを中古で買ってみたりとか。 この原因は色彩検定の資格を出しているところが、過去問ネット上にバラすなよ。 としていることにあります。 それしてしまったら、商売あがったりだからだと思います。 僕も過去問購入しましたけど、だってネットにおちてないんだもの。 他の資格は大体落ちています。がめつ過ぎないか? と感じてしまうわけです。 さて、どうすれば良いか。 僕が実際に勉強して合格した経験にもとづき、お答えします!
色彩検定1級二次試験対策に必要なもの
まずこれだけ用意すれば、合格になるものを書いていきます。 【色彩検定3級の範囲:実技試験にかかわる】 ・色彩検定3級にある慣用色名 ・色彩検定3級にある色の表示(10ページくらい) ・色彩検定3級にある色彩調和(35ページくらい) ・色彩検定3級にある配色イメージ(5ページくらい) 【色彩検定2級の範囲:実技試験にかかわる】 ・色彩検定2級にある慣用色名 ・色彩検定2級にある色彩調和(10ページくらい) ・色彩検定2級にある配色イメージ(20ページくらい) 【色彩検定1級の範囲:テキスト試験の範囲】 ・色彩検定1級からは多く出題されません。(過去問チェックすればよくわかる) 出るには出ますが、一次試験で目を通しているはずなので、まあ大丈夫でしょう。 【実技に必要な道具】 ・ハサミ ・ノリ ・配色カード 以上! 上記を丸っと覚えれば、合格します。 最初の書いたとおり、1級の試験を受けるためには3級・2級のテキストが必須になります。 銭げばぁ~(笑)
色彩検定1級2次試験実技試験について
これを読んで実際に色彩検定1級の二次試験を悩まれてる方! これね、全然実技試験じゃないから、安心して良い!(笑) ただ配色カードっていう紙切って、貼るだけ。 それ実技なん?(笑) ってレベルの試験です。 貼る凡ミスさえなければ、全く問題ありません。 ただ、「芋づり式問題」となっているので、1問目を間違えいる必然的に30点前後持っていかれる仕様です。 えげつない。。 例えばですが、 「清少納言がすさまじき色と評した色は?」→「紅梅色」 「紅梅色をトーン番号で表すと?」→「li+2」 「その色彩番号の対照色相で黄色に近い色は?」・・このように続きます。 その答えた番号の配色コードの紙を切って貼りなさい。 1問目が間違えるとほぼ全てが終わります。 そんな試験が色彩検定1級の2次試験になります。 3級、2級、1級をしっかりと勉強している人は対策何で不要なんだと思います。 ただ、いきなり1級を受けようとしている僕みたいな人は色々と効率の良い促成学習をする必要があります。 本日はここまで。 次回は促成学習について書いていきます。