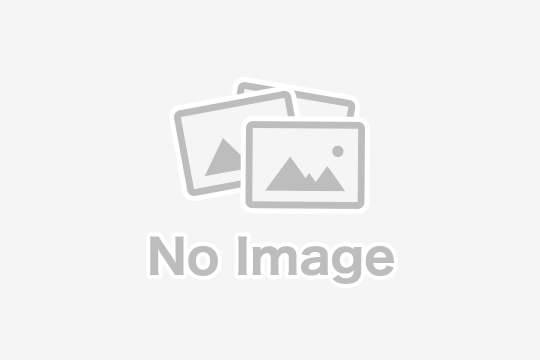独学で色彩検定1級をいきなり取りに行く効率的な学習方法
シリーズものにして、受けようかな?今勉強している人向けに役に立つように書いていきたいと思います。 出来るだけくどくならず、簡単に!
色彩検定について
https://www.aft.or.jp/
前回の続きを話していきましょう。
この学習は二次試験を対象としています。
一次試験は困らないで下さい。
ただただ、愚直に色彩検定協会が出している色彩検定1級の本を覚えて下さい。
出すと言っているところが、そこから出すと言っているので、覚えて下さい。
7週位すれば大丈夫だと思います。
1週目ただただ読むだけ。
2週目個人的に気になることを特に読む。←興味をもって読むことが大事。例えば、葛飾北斎聞いたことがあるな、引越ししまくって無かったっけ?とか脱線するくらいが良い(笑)
一度過去問をやってみる。→ たぶん余裕で落ちる(笑)
3週目、読みながし読みながし、、あ、ここ間違えたところだ!と気に留める
過去問
4週目 だいたいこの辺から出てくるなというのがわかってくる。
過去問
5週目 合格ラインに達しているはず
過去問
6週目 テキストの内容を暗記しはじめる
過去問
7週目 合格圏内にいるが満点取ってやろうか?
こんな感じでやれば、1次試験はまあ、受かるでしょう。
さて、話がそれました。
2次試験の話に戻ります。
効率よく二次試験を合格する学習方法
まず慣用色名を126色覚える!
・・・何が効率が良い勉強の仕方だ!嘘吐き!!
ハハハッ、嘘ではありません。
これをおぼえなければ、お話になりません。
これがむしろ一番の難所、つまり他は大したことがないということ。
それでは覚える方法についてやっていきます!
めちゃ重要なので、読みながさないように!
まず、1級のテキストにはこういった感じで書いています。
__________________
「茜色(あかねいろ)」→①色名
「茜は日本の山野にも自生するつる草。その根を原料とする染料で染めた濃い赤を表す色名。茜色に照りはえる、という意味の枕詩「あかねさす」は「万葉集」にも用いられた。日本で最古の植物染料の1つ。」 →②歴史的な話
「こい赤」→③色分け
「4R 3.5/11」→④色分けを数値化したもの
__________________
①色名 → 必ず覚えてください。
②歴史/由来 → 覚えなくてもよいやつが半分くらいある
③色分け → 色を見た目でわかっていれば、覚える必要なし
④数値化 → 目安程度なので、別に覚えなくても良い。
⑤トーン記号と番号 → dp2 *これ書いてません*
めちゃくちゃ重要なんだが、⑤は書いていない。→ 自分の感覚で覚えなさいというこです。(笑)
いや、マジ笑いごとじゃないんだが。。。
→ 大事なのは色名と実際の色をイメージできるか。
↑とくにこういったものが色彩検定2次試験対策として販売しています。
慣用色名の覚えなくても大丈夫パターン
全部で126種類だか、127種類だかあります。
覚えるのたいへんですよね。。
わかります、わかります。
では、覚えるものではなく、覚えなくても大丈夫な方法を考えていきましょう。
僕は試験を受ける時はテストを作る側の気持ちで考察してから学習に取り掛かります。
どういうことかというとですね。
例えば、先ほどの「茜色」を試験に出したいとなった時、あなたならどういった問題を作るでしょうか?
使えそうな文言は「茜色」「あかねさす」「万葉集」「日本最古の植物染料」「dp2」ですかね。
なぜそんなことが言えるかというと、仮に「こい赤」で試験を作った場合、「こい赤」って色多すぎじゃね?茜色に絞るの難しいし、テスト終わった後にクレームになってもかなわん。。
と試験問題を作る人はどういった試験を作るかより試験が終わった後に自分の作った試験にミスがないかの方がよっぽど重要なわけです。
これが人の心ってもんよ。(笑)
となると、明らかに「茜色」さす文言が抽出されるわけです。
つまり、この色に関して問題を作るとなると。
「日本最古の植物染料で万葉集にも用いられる」
こんな感じになることが予想される。
つまり、「茜色」は試験を作る立場からすると使いやすい色の一つということになります。
さー、わかってきたでしょうか・
使いがっての悪い色は使われないということです。
__________________
「空色(そらいろ)」
「天候により空の色はさまざまに変わるが、これは晴天の青空に色を表す色名。英語でスカイブルー。多くの言語で明るい青は空の色と呼ばれている。古くから一般的な色名として知られている色」
「明るい青」
「9B 7.5/5.5」
「lt+16」→ これは載っていない
__________________
あなたが問題を作る人だとして、この色を指名しますか?
いやー、簡単すぎて。。となるでしょう。
そういった色は色名は覚えて、歴史や由来はいりません。
だって、それは簡単すぎて覚える必要すらないし、出る可能性は無いに等しいから。
仮に出ても対処可能でしょう。
歴史や由来から、色名を特定させて、そこからトーン記号番号を書かせるパターンです。
逆にいえば、歴史や由来が弱ければ、出ないということです。
でも、色名は覚えて下さい。
そしてその色名を言われた時にどんな色かイメージできるようになるのが大事です。
そんなもんで、慣用色名を効率的に覚える試験対策があれば、最高です!
ヤフオク
https://auctions.yahoo.co.jp/search/search?auccat=&tab_ex=commerce&ei=utf-8&aq=-1&oq=&sc_i=&p=%E8%89%B2%E5%BD%A9%E6%A4%9C%E5%AE%9A1%E7%B4%9A2%E6%AC%A1&x=0&y=0
ヤフオクとかメルカリとかで効率のよい中古で十分なので、購入ください。
特にトーン記号番号を書いてくれているものは大助かりです。
はい、本日はここまで。
次回は慣用色名以外のところを書いていきます。